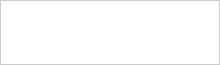礼拝説教の要旨・2025年9月7日・ルカ8:40-56
“恐れないで神の時を信じなさい”
医学が発達していなかった頃のイスラエルでは“きよさと汚れ”という考え方が人々を支配し束縛していた。衛生や健康に問題ないものは“きよい”とされ、問題あるものは“汚れ”とされ“汚れたもの”は食べないし触らなかった。血の流出や死体は汚れたものだった。聖書を読む時、そのことを知る必要がある。イエス様と弟子達がガリラヤ湖西岸のユダヤ人の住む地域に戻ると、群衆が集まり、その中に12歳位の娘が病いで死にかけていた会堂司ヤイロがいた。彼は癒しで有名なイエス様に娘を癒してほしいと思い、ひれ伏して自分の家に来てくれるようお願いした。主と弟子達はヤイロと一緒に出かけ、群衆もついて行った。
その群衆に12年も長血を患う女がいた。彼女はいろんな医者にかかったが、治らず財産を費やすだけだった。彼女は癒しでイエス様なら必ず癒してくださると信じて後ろからイエス様に近づき、その衣の房に触った。ただちに出血が止まった。主はそれに気づき、触った人を捜し出した。その様子を見ていた彼女は、隠しきれないと思い、震えながら進み出て、触った理由と癒されたことを話した。当時、出血が続く病いは汚れた者と見なされ、他の人に触ることは許されなかったからだ。「娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい」救いとは何か?私達はすぐに魂の救いを考える。だが、彼女の場合、魂の救いだけでなく、癒しがあり、さらに汚れた者と見なされていたことからの解放もあった。当時、祭司がきよくされたことの宣言をする習慣があったが、イエス様の言葉は、彼女は“きよくなった”という宣言であり、彼女は社会に復帰しやすくなった。これも救いである。
一方、長血の女が割り込んできて主が手間取ったことは、ヤイロにとって一刻も早くイエス様に家に来て娘を助けてほしいのに娘が助かる可能性を縮めることだった。ヤイロは黙っていたが、苦しい思いだったに違いない。主が長血の女と話していたとき、「お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません」という知らせが来た。ヤイロはどん底に突き落とされた思いだろう。そんな彼に主は「恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば、娘は救われます」と語った。何を信じるか?神が死んだ者を生き返らせることだ。また死んだ少女を泣き悲しむ人々に「泣かなくてもよい。死んだのではなく、眠っているのです」とも語った。「死」を「眠り」と言う。眠りから目覚めることが復活だ。だからイエス様は「子よ、起きなさい」と言って死んだ娘を生き返らせた。しかも、主は“少女の手を取って”そう言った。当時、死体は律法によって汚れたものと見なされ、死体に触ることは禁じられていた。良いサマリヤ人のたとえ話で強盗に襲われて半殺しにされた人を祭司やレビ人が助けなかったのはなぜか?彼らに隣人愛がなかったのではない。もしその人が死んでいたら律法違反になることを心配したからだ。だが、イエス様は、死体が汚れたものだと思わず、死んだ娘の手を取った。主はそのことを通して律法を越えて隣人に愛を与えることを教えられた。救いと言うと、私達は魂の救いを得て天国に入ることばかりを思う。それは最も大切なことだが、救いはそれだけはない。救いは魂の救いを土台にして、そこから広がりがある。では、私達にとってその広がりとは何か?それは私達それぞれに与えられた宿題である。