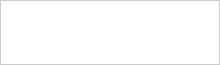礼拝説教の要旨・2025年9月14日・ルカ9:1-6
“私たちの必要を満たす神への信頼”
主は自分が十字架のみわざを終えて世から去り天に帰った後も、自分の働きを継続するために12人の弟子達を集めて訓練し、働き人とした。だからイエス様の働きは引き継がれて発展した。今の私達も働き人を育てる必要があるが、主のなさったことは参考になる。8章では12弟子は主のお供をして見様見真似で宣教のみわざを学んだ。9章では実際に宣教の働きをして学んだ。それが伝道旅行だ。主は弟子達に悪霊を制し、病を癒やす権威を授けてその奉仕を任せた。その目的は「神の国を宣べ伝え、病人を治す」ことである。
では、どんな伝道旅行だったのか?現在、旅に出る場合、旅費、余分の下着、袋、小銭など必要なものすべてを揃えるが、主は必要最小限の持ち物以外は何も持たないようにさせた。マルコは1本の杖をOKとしたが、ルカは杖もダメだと言う。ただしイエス様はいつでもそうしなさいと命じたのではない。十字架が近づく22章のゲッセマネの祈りの直前に主は財布や袋や剣を持つように勧めた。主は弟子達の生活の必要を準備することを教えたし、何もなくても主が必要を満たすという主への信頼も教えた。私達には両方とも必要だ。だから何も持たない極端な生き方をする必要はない。主はなぜ何も持たない伝道旅行を教えたのか?その理由は「どの家に入っても、そこにとどまり、そこから出かけなさい」にある。家とは弟子達を理解して受け入れ、宣教を支えてくれる協力者だ。協力者が宣教のために必要なものを与えて支えてくれるから必要最小限のものだけを持ち、伝道旅行に出かけるのである。使徒16章でピリピ伝道をしたパウロにはリディアがいた。彼女は「私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊りください」と懇願したのでパウロ達はリディアの家を拠点にして伝道し、さらに彼女の家から次の伝道地に送り出された。
けれども、反対に協力者が現れず、人々も弟子達を受け入れない場合は無理してその町に留まる必要はない。「その町を出て行くときに、彼らに対する証言として、足のちりを払い落としなさい」たとえば、使徒13章でパウロやバルナバはピシディアのアンティオケの会堂でみことばを語るとたくさんのユダヤ人や神を敬う異邦人が集まり、みことばを聞いたが、ユダヤ人達はパウロの語ることに反対し、口汚く罵り、さらに宣教を妨害し、パウロ達を追い出そうとした。それでパウロ達は「私達はこれから異邦人達のほうに向かいます」と言い、足のちりを払い落して袂を分った。ところで、なかなか導かれない人達とも期待しながら関係を保とうとする私達にとってこのみことばは理解しがたい。でも、今回、語る機会が与えられ考え直してみて、あることが示された。それは人を救うのは私達ではなく神だということだ。確かに私達は人が救われるために祈り、みことばを伝え、愛を注ぐが、その人を悔い改めさせ信仰を与えるのは、私達ではなく聖霊なる神だ。聖霊は私達の手に余る人をも救うことができる。イエス様に激しく敵対していたサウロを当時のキリスト者達は恐れて“足のちりを払い落とした状態”だったが、聖霊は不思議な方法で彼を信仰に導いた。だから“足のちりを”とは自分の無力を認めて手に負えない人を主の御手に委ねることだ。その人を見捨てたのではない。主がその人を導いてくれるだろうという主への信頼があるのである。